概要outline
心臓内の弁や心内膜に細菌(まれに真菌)が感染し、疣贅(ゆうぜい)と呼ばれる菌塊を形成する疾患です。1日に心臓の弁は数万回も開閉するため、小さな傷に血中の細菌が付着して塊を作り、弁を破壊して重篤な症状を引き起こします。頻度は高くありませんが(一年間に人口10万人あたり10~50人程度)、診断が難しく重篤化しやすいため注意が必要です。
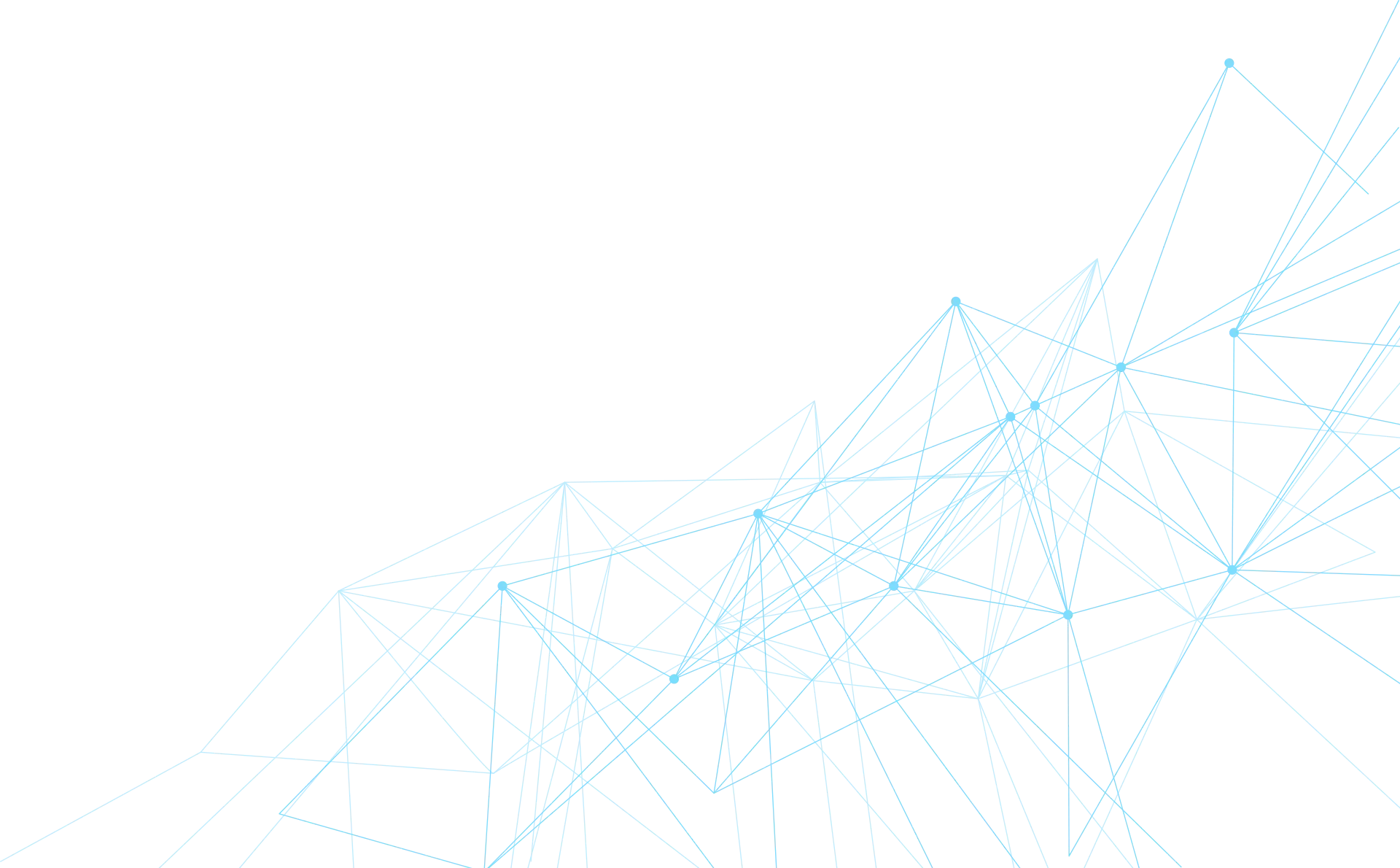

心臓内の弁や心内膜に細菌(まれに真菌)が感染し、疣贅(ゆうぜい)と呼ばれる菌塊を形成する疾患です。1日に心臓の弁は数万回も開閉するため、小さな傷に血中の細菌が付着して塊を作り、弁を破壊して重篤な症状を引き起こします。頻度は高くありませんが(一年間に人口10万人あたり10~50人程度)、診断が難しく重篤化しやすいため注意が必要です。
先天性心疾患(心室中隔欠損など)や弁膜症で心内膜に損傷がある患者、人工弁置換後の患者では発症リスクが高くなります。また高齢者で弁の石灰硬化がある場合、長期透析患者、免疫抑制剤使用者、低栄養状態、がん患者でも注意が必要です。菌血症のきっかけとして歯科処置や抜歯、扁桃摘出、内視鏡検査、泌尿器・婦人科処置などがあります。日頃から口腔衛生を保ち、侵襲的処置の際には必要に応じ予防的抗菌薬投与が推奨されます。
長引く発熱(微熱が続く)、悪寒戦慄、全身の倦怠感、食欲低下、体重減少など非特異的な症状が多く、しばしば他疾患と紛らわしい経過をとります。進行すると感染した弁が破壊され心不全症状(息切れ、むくみ)が現れたり、菌塊の一部が血流に乗り飛んで塞栓症を引き起こします。脳血管に飛べば脳梗塞、腎なら腎梗塞、肺なら肺塞栓、眼や四肢の動脈閉塞など、多彩な合併症を起こし得ます。皮膚や眼球結膜に点状出血が見られることもあります。
臨床症状に加え、経胸壁心エコーで疣贅の付着を探し、確証が得にくい場合はより感度の高い経食道心エコー検査を行います。また血液培養で原因菌を検出し、これら所見を総合して診断します。確定診断基準として改良Duke基準が用いられ、主要所見(血培陽性・心エコー所見)と副次所見(所見や背景因子)を組み合わせて判定します。
発見次第ただちに抗菌薬の大量静注を行い、少なくとも4~6週間にわたる長期投与で感染巣の根絶を図ります。起因菌に合わせた抗生物質選択が重要で、治療経過中は血培の陰性化と炎症反応の改善を確認します。心不全の悪化(弁穿孔など)や難治感染、塞栓予防の観点から、状況によっては外科手術(感染弁の切除・人工弁置換)が検討されます。感染コントロール下での計画手術が望ましいですが、急性期合併症では緊急手術もあり得ます。治療中は塞栓症の有無を脳MRIやCTでチェックし、必要なら対応します。治療完了後も再発防止のため定期的な歯科受診や感染予防策が重要です。
| 受付時間 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜 12:00 |
29診 | 2階 | 川本 浩禎 | 藤野 祐介(心不全・弁膜症外来) | 角野 元彦 | 北原 慧 | 角野 元彦 |
北原 慧※第1・3・5週担当 角野 元彦※第2週担当 神吉 秀明(心不全・弁膜症外来)※第4週担当 |
| 30診 | 大西 宏和(心不全・弁膜症外来) | 神吉 秀明 | 新居田 登三治 | |||||
| 31診 | 桑山 明宗 | |||||||
| 14:00〜 17:00 |
29診 | 2階 | 藤野 祐介 | 藤野 祐介(心不全・弁膜症外来) ※第3週は休診 |
神吉 秀明(心不全・弁膜症外来) | 北原 慧 | ー | |
| 30診 | 神吉 秀明(心不全・弁膜症外来) | 角野 元彦 | 大西 宏和 | 新居田 登三治 | 桑山 明宗 | |||
| 31診 | 今岡 拓郎 |
| 受付時間 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 28診 | 2階 | ー | ー | ー | ー | 上田 希彦 | ー |
| 14:00〜17:00 | 28診 | 2階 | 上田 希彦(デバイスのみ) | 榎本 典浩※第2・4週のみ | 上田 希彦 | ー |
7:30~17:30(月~土) 診察の予約・変更及び検査の変更ができます。