概要outline
心筋への血液供給が一時的に不足し、胸痛などを引き起こす状態です。冠動脈の動脈硬化による狭窄が主因で、安定狭心症(症状が慢性的に安定)と急性冠症候群(不安定狭心症や心筋梗塞に移行する重症例)に大別されます。日本人では冠動脈の一過性の攣縮(けいれん)による冠攣縮性狭心症も多くみられます。
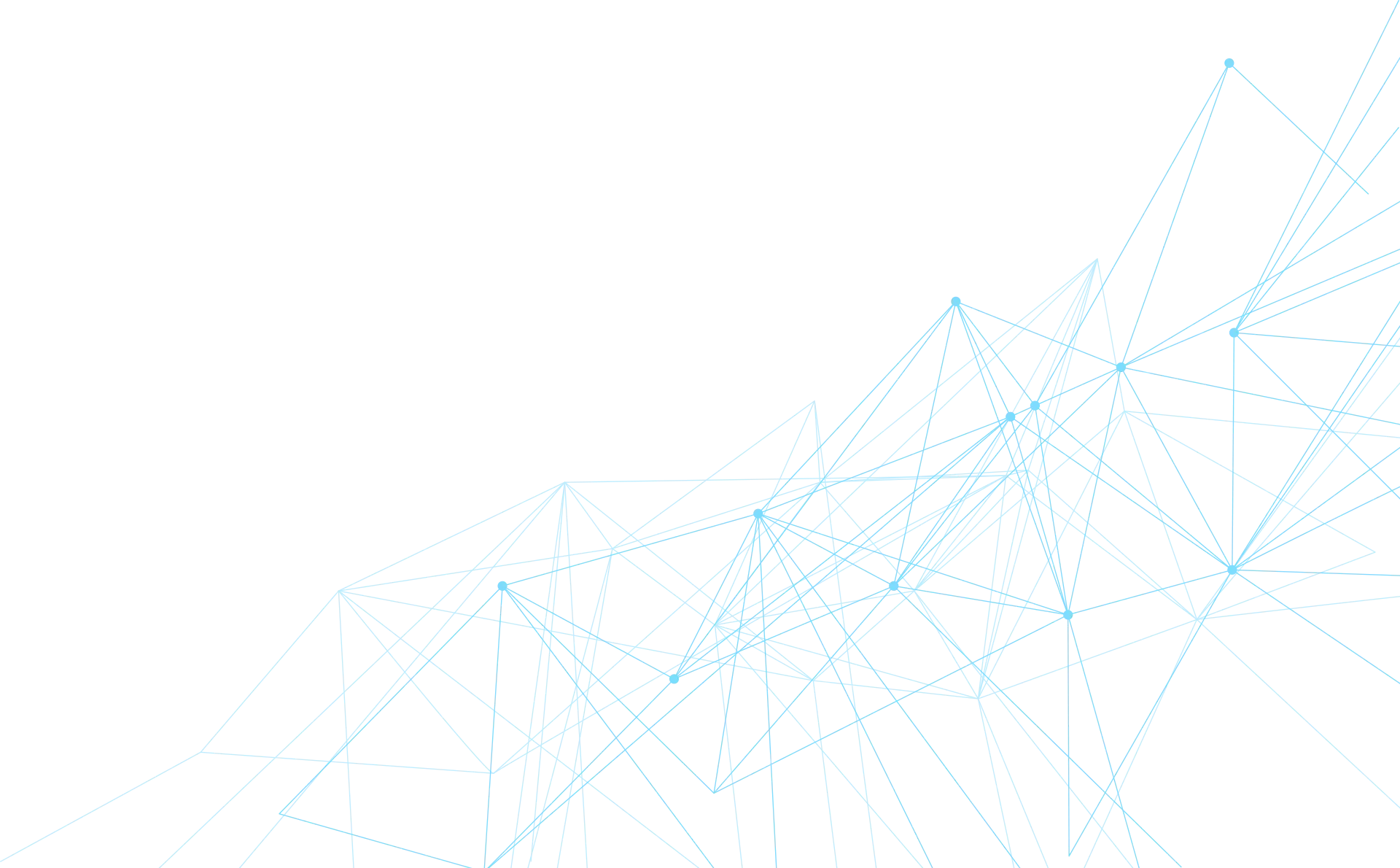

心筋への血液供給が一時的に不足し、胸痛などを引き起こす状態です。冠動脈の動脈硬化による狭窄が主因で、安定狭心症(症状が慢性的に安定)と急性冠症候群(不安定狭心症や心筋梗塞に移行する重症例)に大別されます。日本人では冠動脈の一過性の攣縮(けいれん)による冠攣縮性狭心症も多くみられます。
胸の中央が締め付けられるような圧迫感・痛みが特徴です。労作性狭心症では階段昇降や運動など一定の負荷で症状が出て、安静で数分以内に軽減します。安静時狭心症(冠攣縮性)では早朝や安静中にも起こり、数分~15分程度で消失するものの再発を繰り返します。発作中は蒼白、冷汗、動悸を伴うこともあります。症状が徐々に悪化したり安静時にも出現する場合は不安定狭心症と呼ばれ、心筋梗塞への進行リスクが高いため緊急治療が必要です。
安定狭心症では運動負荷心電図や負荷心臓エコー・心筋シンチで誘発される虚血変化を確認します。また冠動脈CTで血管狭窄の有無を非侵襲的に評価できます。確定診断には冠動脈造影(心臓カテーテル検査)を行い、狭窄部位や重症度を直接観察します。冠攣縮性狭心症が疑われる場合、カテーテル検査時に薬剤で痙攣を誘発する試験も実施されます。
病状に応じて (1) 薬物療法、(2) カテーテル治療(PCI)、(3) 冠動脈バイパス手術を選択します。薬物療法では硝酸薬やβ遮断薬、カルシウム拮抗薬、抗血小板薬などで心筋酸素需要を減らし症状を予防します。狭窄が強い場合はPCIでステント留置による血流改善を図ります。複数血管にわたる重症例では外科的に新たな血行路を作るバイパス術が検討されます。治療後も危険因子の管理が重要で、高血圧・糖尿病・脂質異常症のコントロールや禁煙、適度な運動により再発予防を行います。
| 受付時間 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜 12:00 |
29診 | 2階 | 川本 浩禎 | 藤野 祐介(心不全・弁膜症外来) | 角野 元彦 | 北原 慧 | 角野 元彦 |
北原 慧※第1・3・5週担当 角野 元彦※第2週担当 神吉 秀明(心不全・弁膜症外来)※第4週担当 |
| 30診 | 大西 宏和(心不全・弁膜症外来) | 神吉 秀明 | 新居田 登三治 | |||||
| 31診 | 桑山 明宗 | |||||||
| 14:00〜 17:00 |
29診 | 2階 | 藤野 祐介 | 藤野 祐介(心不全・弁膜症外来) ※第3週は休診 |
神吉 秀明(心不全・弁膜症外来) | 北原 慧 | ー | |
| 30診 | 神吉 秀明(心不全・弁膜症外来) | 角野 元彦 | 大西 宏和 | 新居田 登三治 | 桑山 明宗 | |||
| 31診 | 今岡 拓郎 |
| 受付時間 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 28診 | 2階 | ー | ー | ー | ー | 上田 希彦 | ー |
| 14:00〜17:00 | 28診 | 2階 | 上田 希彦(デバイスのみ) | 榎本 典浩※第2・4週のみ | 上田 希彦 | ー |
7:30~17:30(月~土) 診察の予約・変更及び検査の変更ができます。